|
|
|
「廻廊」とも書き、寺院や神社で中庭を囲むように巡らされた屋根つきの廊下。 東大寺、法隆寺など古代の寺院に見られるものを別とすれば、近世の寺院では主として禅宗の寺に見られる。禅宗の寺院に見られる回廊は古代の寺院の伽藍配置が継承されたものではなく、鎌倉時代以降に禅宗の渡来とともに再度輸入されたものと考えられる。 以下に岐阜県関ヶ原町妙応寺の例を見てみる。 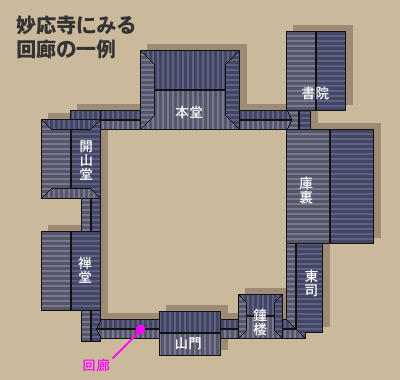 禅宗の回廊寺院は一般的に、本堂を正面に、向かって左に禅堂、向かって右に庫裏(くり)を配し、手前の山門までを四角く囲むように作られ、いわゆる回廊という建築物はその各種堂宇の間をつなぐように設置される。 上図をみても想像できる通り、通常は回廊を通りながら堂宇を次々に巡り、一巡することが可能である。もちろん私は参詣時には可能なかぎり回廊内を旋回することにしているが、お寺にしてみたらこうした行為は迷惑以外の何ものでもなく、回廊本来の機能とは言えない。禅宗寺院において回廊の主要な機能は生活の場である庫裏(や衆寮)と修業の場である禅堂との間を結ぶ通路であって、回廊部分を積極的に旋回するための構造ではないのだ。 しかし、単に庫裏と禅堂の間の移動というだけであれば、渡り廊下を掛けるだけでよいわけで、あえて360°を囲む空間を作り出しているという点において、やはり回廊は旋回可能な空間と位置づけざるを得ない。もちろん、これは参拝者のための空間ではないのだが、特殊な空間としてカテゴリを設けることにした。 |
|
  |
 回廊とは?
回廊とは?