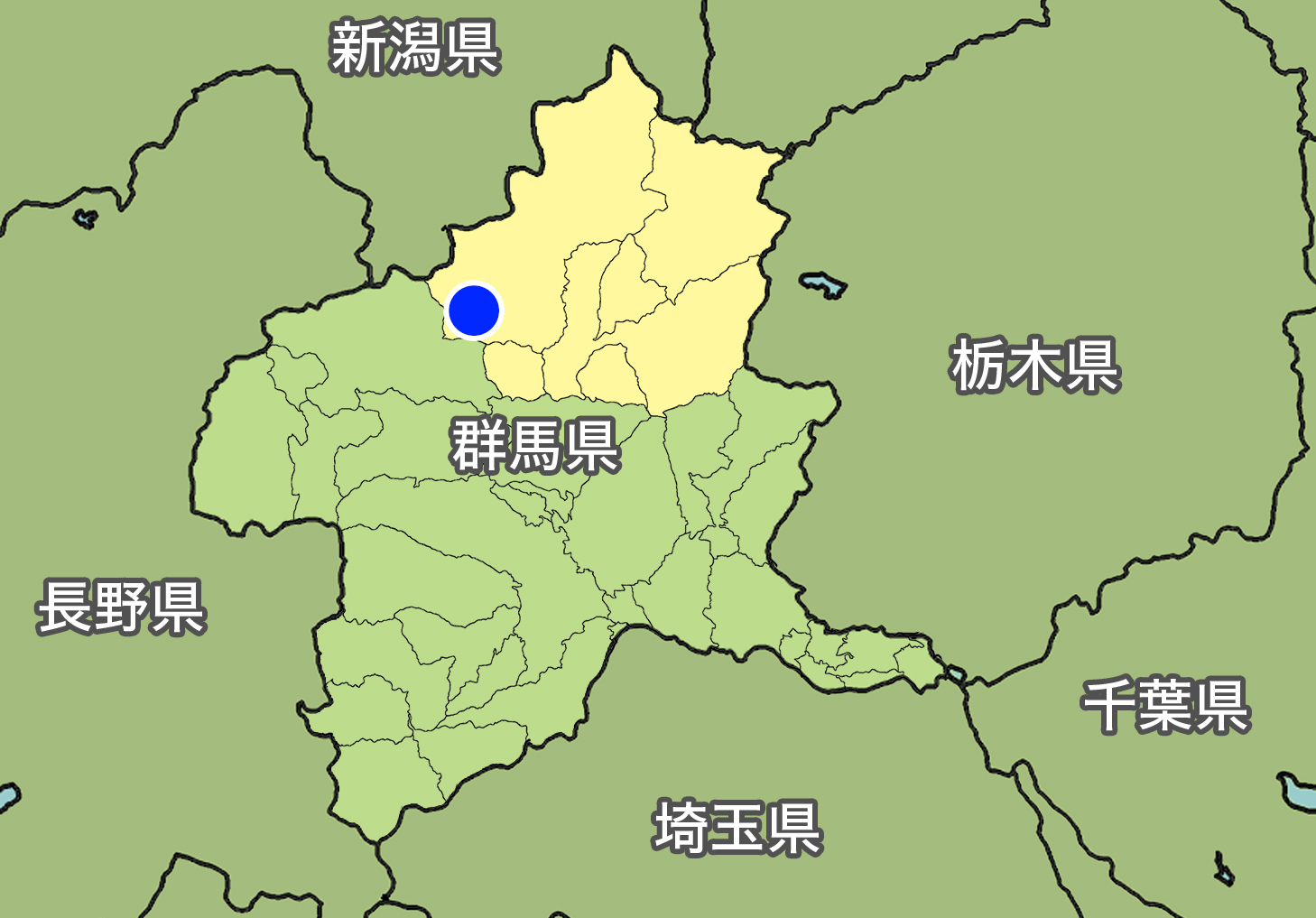大道峠を越え、旧新治村へ降りてきた。
辺りは代かきが終わった田んぼと、春の花が咲き乱れる美しい季節。
中央に見える大屋根は日帰り温泉の「奥平温泉」。遠くには三峰山のまっすぐ延びた稜線が見える。


集落には大きな屋根の養蚕農家が目立つ。
小豆色の屋根は、妻兜、榛名型突き上げ、三ツ櫓という豪勢な造り。
その手前にある大きな倉庫のような建物はおそらく蚕室だ。側面に掃出し窓が連続していて、作業性がとても良さそう。

この農家の主屋の寄棟のトタン葺きの屋根はもとは茅葺きで、建築当初の形は単純な寄棟か入母屋だった可能性がある。
いわゆる兜造りや、榛名型/赤城型といった採光と換気を意図した屋根に改造することが流行したのは明治以後というハナシもあるからだ。

こちらは2階が屋根の中に埋没している榛名型屋根を持つ養蚕農家。
榛名型/赤城型という言い方はあくまでも研究者がつけた名前であり、当時の大工がそう言っていたわけではない。またこの屋根のように、中間のような形態もある。

榛名型/赤城型はいずれも屋根に切り欠きを入れるので雨じまいはよくないはずで、日本家屋の悠久の歴史のなかでは明治中期ごろのあだ花的な屋根の形と言ってしまってもいいかもしれない。
ただ積雪を考えると赤城型に比べ榛名型のほうが有利と思われ、この地域に榛名型が多いのは降雪量が影響しているのではないかと想像している。

こちらは出し梁造りの越屋根つき切妻屋根の農家。
内部は3階建てになっているのではないか。
(2017年05月07日訪問)