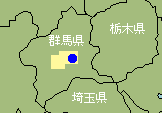東大室稚蚕共同飼育の最大の特徴は、土室育時代のムロが残っていることだろう。
通常は、土室育方式の飼育室として造られた飼育所も途中からは電床育方式に切り替えられ、内部は電床育の装置が設置されている場合が多いとされている。
しかし、ここでは電床育方式で使用された痕跡はなく、土室育で使用されたままの状態が残っている。どうしてそうなっているかは謎だが、おかげできわめて貴重な史料を後世に残すことになったのは喜ばしいことだ。

土室育は、群馬県の蚕業試験場で昭和25年ごろ考案された飼育方式で、別名「群馬式簡易稚蚕共同飼育法」とも言われる。終戦後の物資の少ない時代にも建設運用できたすぐれた方式で、稚蚕共同飼育を普及させるきっかけにもなった。養蚕の歴史の上できわめて重要な発明であった。
構造は写真のとおり。約1m四方の小部屋を土壁で造り、それを横に連結した構造になっている。この小部屋のことを「

内部は、土間より少し掘り下げられていて、床砂が敷かれている。この場所に火鉢などを置き、室の内部を加温したのだ。
蚕箔を取り付けるラックの跡が見える。このうち最下段の蚕箔(火鉢の直上)には保湿用の盛り砂を置いた。また、温度差により生育に差が出ないように、蚕箔はときどき上下をローテーションしなければならず、1段は入れ替えのために空けておいたという。つまりラックが12段あれば、蚕箔は10段セットできることになる。
奥に見える土管は、火鉢の換気のためのものだ。

土管は外部に出ているので、土室式の蚕室を持つ飼育所は、この土管により外から確認することができる。
上細井の物件では、土管の穴がコンクリでふさがれてたが、ここではちゃんと抜けている。

土室の扉は木製だが厚さがあり、内部は中空の二重扉になっている。
また、中央にはガラス窓があって内部の温度を確認できたようだ。土室育専用の温度計というものもあったという。ガラス管がL字型になっていて、先端部のみをムロの内部に挿入し、温度を読む目盛りは外部に出ているというものだ。だが、この土室ではそのようなタイプの温度計を差し込む穴は見当たらなかった。
ガラス窓にフタがあるのは、カイコが光に集まってしまうのを防ぐためなのだろう。稚蚕は真っ暗なムロの中で飼育されていたのである。

天井には排気管の穴がある。片方を引くと、両方が開くようになっているものの、ムロの外からは操作することはできない。この構造は土室としては一般的なもののようだ。
外部から操作できないということは、おそらくこまめに開け閉めしたのではなく、一定の幅で空けて通気させたのではないかと思う。

排気管の上部には、土管でできた煙突が出ている。
和紙のようなものがかぶせられているが、これが何のためなのかはわからない。
いずれにしても、ムロ内の空気は下部の土管から流入し、上部の土管から排出されるという仕組みだったことがわかる。

下部の壁面には、四角い穴1つと、丸い穴2つをふさいだ跡があった。
土室育に関する資料では、土管はムロの手前と奥の両側に2本ずつあり、さらに手前側中央には開閉式の四角の穴があって、炭の管理をしたり換気量をコントロールしたらしい。だがこの部分の使用法については、私が何人かに聞いた限りでは、はっきりとしない点も多い。
練炭を使ったことがある人はわかると思うが、炭の火力コントロールには酸素を遮断する方法を用いる。土室もそのような方法で炭の火力をコントロールしていたというのだ。

だとすると、火力を下げるときにはムロの内部は酸欠状態になるわけだが、稚蚕が消費する酸素は非常に微量であるため、特に問題にはならないのだという。また、カイコは一酸化炭素中毒にはならないらしい。
だが、人間にとっては一酸化炭素中毒は重大な問題である。一酸化炭素は空気より軽いので通常の運用では上部の煙突から抜けたと考えられるが、屋外の風圧によって、下部の吸気管から逆流することも考えられなくはない。そのような事故を防ぐために、室内側の吸気管はふさいだのではないか。
写真中央部の砂の中に見える丸いものは、火鉢を置いた台と思われる。室内側の吸気口はふさがれているのが確認できる。

建物の奥半分は、ブロック電床育タイプの飼育室になっている。一つの建物の中で形式が混在していたことになる。
ブロック電床育の飼育室はこれまでも紹介したが、ここではかなりはっきりとわかるのでじっくりみてみよう。
向かい合ったムロとムロのあいだは広い通路があるが、ここに蚕箔を取り出して、給桑したのである。通路というよりは給桑室と呼ぶべき空間なのである。

ムロの内部は軽石ブロックがむき出しになっている。モルタルなどで被覆されていないのは手抜きなのではなく、保湿のために壁面に水をかけたからなのだという。
このムロは3列、10段程度の蚕箔がセットできるタイプだ。
手前に出ているのが保温のための電熱線。ムロ内に固定されていたのではなく、取り外せるようになっていた。飼育開始前には当然この電熱線も消毒されたはずである。

床部は土間より少し掘り下げられていて、発泡樹脂の断熱材が敷かれていた。ムロの天井も同様である。
電熱線はムロの下部にはめ込まれていたわけだが、壁に水をかけるときには、当然電熱線にも水がかかったと思われる。だが、それにはおかまいなしに水をかけていたという証言もある。漏電しないような仕組みだったのだろう。
初期のブロック電床育では、下部には床砂を敷いて保湿をしたと想像しているが、その際も電熱線の上から水をかけていたと思われる。

電熱線のスイッチ。出力は500Wだったという。
上部に見える電球はパイロットランプであり、このランプを見ながら、スイッチのON/OFFを手動でコントロールしていたのだろう。
ムロ内の天井から下がっているのはサーモスタットではないだろうか。

東大室稚蚕共同飼育所は、おそらく前橋市内で唯一残存する土室育形式の飼育所の遺構であろう。また寡聞にして、群馬県内で(電床育に改造されていない)土室育の飼育室の遺構があるという話は聞いたことがない。
土室育は別名「群馬式」とも言われるほど、群馬県と関わりの深い産業技術である。これはまぎれもなく群馬県が後世に伝えなければならない史料なのだ。早急な保全が望まれる。
(2007年02月13日訪問)