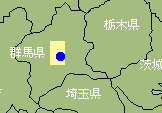稚蚕飼育所巡りが一段落し、2009年~2011年ごろ私は主に養蚕農家めぐりをしていた。その2011年の6月上旬、有馬の養蚕農家、一倉家を再訪した。
2008年に訪問したとき、今度はカイコのいるときにおいでとおっしゃってくださったので、もう覚えていないかもしれないが訪問してみた。

すると、なんだか景色が違う。屋敷林がなくなっているのだ。屋敷森はケヤキが中心で、それを材木として売って母屋の屋根を葺き直したのだという。
この母屋自体が、古い時代に屋敷森から切り出した材木で建てたと聞いているので、一倉家では森の再生にあわせて建物を更新しているのだ。

母屋と道を挟んで南側には碑がある。これは一倉家の先祖が「一倉飼い」という飼育方法を考案して、地域に広めたことについて書かれているそうだ。
一倉飼いとは、薪を焚いて蚕室内を加温することで、カイコの成長を促進するという方法だったという。一般的には「温暖育」と呼ばれるものに近い考え方だ。
明治以前、養蚕農家にとっての飼育期間は40日あったという。それを温度を掛けることで短縮し、農家の労力を減らし、他の作物との複合経営をやりやすくしたという点で、近隣の養蚕家に感謝されたという。

ここでいう40日という飼育日数が、掃き立て(孵化)から繭かき(蛹化)までのことだとすると、現代ではそれを30日でこなす。現代の飼育でも1~3齢は徹底した加温管理なので一倉飼い(温暖育)に近い。一倉飼いはおそらく10日の短縮を実現したわけで、田植えなどの他の農作業の時間を確保できる画期的な手法だったろう。
碑文の文字は「一倉勝号(?)先生之碑」であろうか。

訪れたのは、5齢の5日目くらい。養蚕のクライマックス、一斉上蔟まで残り3日というところだった。
左写真が現在の一倉家の飼育スタイル。
群馬県の一般的な養蚕農家とはかなり違っている。群馬県の通常の飼育スタイルは、(1) 機械式の多段循環蚕座、(2) スチール製スーパー飼育台、(3) 木製のテーブルの上と下での平飼い、が一般的。だがここでは蚕室は土間の上に蚕箔を並べての平飼いなのである。あえていえば、(3)のテーブルの下だけが並んでいる状態とも言える。

さらに拡座の方法が独特なのである。
配蚕時には蚕箔は2枚を重ねて飼育を始める。カイコが成長して蚕座が狭くなると、スライドさせながら飼育面積を拡げていくのだという。
上蔟が近いということもあって成長の早い「ズウ(熟蚕)」になったカイコがいくらか出ていて、分けてあった(左写真)。

しばらく、給桑の様子を見学させてもらった。
貯桑場は母屋内の土間で、そこに竹のスノコと寒冷紗を敷いている。
桑の束ひとつの重量は7~8キロはあろうか。お年寄りには重労働で、健康でなければ続けられない仕事だ。

枝の置き方は、ひっくり返すような置き方。この置き方のほうが桑がしおれにくいなどというが、農家によっては言うことがまちまちだ。正立させて置く農家も多く、どちらがよいのか、よくわからない。

蚕室は2棟ある。
貯桑場から蚕室までは、敷地内の遠くない移動だが、リアカーを使っていた。こうしたひとつひとつの所作が最適化されているところが、農家の仕事のみどころでもある。

給桑の光景。
飼育台を使わないやり方のメリットは、ひと目でカイコの全体の様子がわかることと、後片づけや
私が聞いた限りでも、多段循環蚕座のような囲いの中に桑を積んでいく方法は、食べ残しの取り出しがやりにくいという話は何度かあった。

枝の置き方も独特。蚕箔に対して斜めに並べている。
一般的に枝の置き方は、鉄道の枕木のように並べる方法と、鉄道のレールのように並べる方法がある。前者の並べかたは後片づけがやりやすいが、カイコに枝の同じ部位の葉が繰り返し載る傾向があるため、栄養が偏ると言われている。後者は逆の長所・短所になる。
一倉家のやり方は、斜めに置くことで、両方のいいとこ取りになっているのだ。

蚕室内には炉があって、桑の枝や根などを燃やしている。
こんなところに、かつての一倉飼いのおもかげがしのばれる。
現在の一倉家のスタイルは、飼育台にしても燃料にしてもお金をかけないことだという。結局、高価な資材を利用している農家は、養蚕を続けられず撤退していったことを考えると、このやり方はまちがっていなかったのだろう。

現在主力の桑品種は「一ノ瀬」だが、以前にこのあたりでは「アカキ」という品種を使っていた時代があるそうだ。畑に少し残っていて収穫した中に混ざっていた(左写真)。葉が取れやすく葉をもいで与えていた時代には便利だったが、葉が細くて薄いので現代ではまったく使われなくなった。
農業生物資源研究所の桑品種のデータベースによると「群馬
上蔟前の比較的忙しい時におじゃましてしまって申し訳なかったが、一倉家の養蚕を見て、こうして記録に残せたことは本当によかった。
(2011年06月04日訪問)