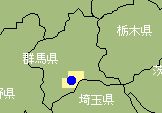2013年、「富岡製糸場と絹産業遺産群」が世界遺産登録の審査手続きに入った。これから紹介する「高山社」の跡地はその構成遺産リストのひとつである。
「高山社」は明治時代に養蚕技術普及のために存在した結社だった。以前は個人の住宅だったため特別な見学日以外は敷地に立ち入ることもできなかったのだが、世界遺産登録に関連して常時見学できるようになった。

古い建物は長屋門と主屋のみで、それも明治24年の建物だという。高山社が成立したのは明治3年で、同18年には藤岡市内に移転しているので、現在残っている建物は、いわゆる高山社そのものの遺構ではない。
世界遺産登録にはまず国内での文化財指定が必要になるのだが、文化庁も高山社跡の現状ではさすがに有形文化財として国重文にするのは無理があると思ったのか、2009年に国指定史跡として登録した。国指定史跡は通常は埋蔵文化財などを指定するものだ。苦肉の策だったのではないか。

主屋は二階建てで、出梁造ではなく、二階に縁がない構造だ。以前、甘楽町でも同様の構造の農家を紹介しているが、数はあまり多くないように思う。「高山社型民家」と呼んでもいいかもしれない。

展示されていた高山社当時の模型。
敷地の右側に桑園と蚕室、左側に主屋(上蔟室)があった。
また、敷地奥側にある小さな小屋は、貯桑室である。貯桑室とは、畑で収穫した桑をいったん蓄えておく場所で、こうすることで夜間や雨天時にも安定して桑を給餌できるようになる。しかし、この配置では、畑→貯桑室→蚕室の動線が悪く、かなり作業しにくかったと思う。

建物は一階が公開されている。
この建物の見どころは二階だと思うのだが、残念ながら二階は見ることができない。以前は特別な公開日には二階に登れたこともあったという。
整備がが進めば、もしかしたら二階に登れるようになるかもしれないが、文化財的な厳格な復元をしたら、急な階段かはしごで登ることになるだろうから、もう、一般の観光客が二階を見ることはできないかもしれない。

奥の間には、蚕に繭を作らせる「改良藁まぶし」や、養蚕信仰に関係深い、餅花、削り花などが展示されていた。一見すると「ああ、むかしの養蚕農家だな」と思わせるこの展示だが、改良藁まぶしが発明されたのは明治後半と考えられ、高山社が養蚕技術を確立させた明治初期とは年代が大きく異なる。世界遺産の価値に見合う、ちゃんとした時代考証をしているのだろうか。ただ古道具を並べればいいというものではあるまい。
削り花も、吾妻地方で開催された勉強会で習ってきたものを、他の地域の古民家で展示している例があり、見るときには注意が必要なアイテムである。

現在の高山社主屋の特徴は、一階の暖気を二階に上げるためのすのこ天井と、床に埋め込まれた火鉢である。
こうした構造は、群馬県の養蚕農家のテンプレートとなった伊勢崎市の島村地区ですでに考案されていたものだが、それを継承したものであることが確認できる。

展示の一つ。気温を記録したグラフ。
高山社は、明治初期に「
だが、そこで出た結論は「気温が低すぎたら暖める、気温が高すぎたら換気する」ということであった。このようなことはおそらくほとんどの養蚕農家が体験的に理解していたはずで、それゆえに「清温育」の価値は理解しにくいと私は感じている。

そこで私なりに清温育の意味をとらえ直してみたいと思う。(かなり個人的な意見なので、藤岡市の小中学生の皆さんは、夏休みの宿題などでは決してこの稿を参考にしないように注意してほしい。)
養蚕は江戸中期には各地の藩によって推奨されていたが、幕末の横浜開港によってそれまでとはケタ違いの需要が発生し、カイコの大量飼育が必要となった。そのため、全国でさまざまな「○○育」というような飼育技術が研究されるようになる。

さて、現在、養蚕農家というと、中山間地でおじいさんおばあさんがたずさわる「のどかでつつましい産業」というイメージだが、明治初期にはまったく様相が違っていた。
当時、生糸や蚕種は輸出額の半分近くを占め、日本をわずかな期間で後進国から抜け出させた、日本史上例を見ないすさまじい経済成長の原動力となった産業だったのだ。当然、それを主導したのは金に目がくらんだ資本家、山師同然の仲買人などであったろう。いまで言えば、堀江貴文や三木谷浩史みたいな俗物ばかりだったはずだ。

そうした養蚕の素人が突然、養蚕業に大量に進出したのだ。「養蚕農家」と言っても、実際は土に触ったこともないような資産家が、使用人を使って無理に大規模養蚕を始めたような例も多かっただろう。そのため明治初期の養蚕は失敗も多かった。
その混乱の中で、まず「

高山社を設立した高山長五郎は、後進でもあったため温暖育と清涼育のいいとこ取りをして、「寒いときには加温、暑いときには換気」という方法を提唱する。これが「
なんだか、聞けば聞くほどに「一周まわって元に戻った育」としか思えない。
養蚕において普通にカイコに向き合っていれば、気温が低いときにも、高すぎるときにも餌を食べなくなることは一目瞭然であり、なぜ田島弥平や高山長五郎は気付かなかったのであろうか。
邪推だが、こうした明治初期の養蚕家は資産家であり、自分自身があまり農業が上手ではなかったのではないか、と疑ってしまう。特に高山長五郎は、養蚕を手がけてから最初の5年間、一度も飼育を成功させることができなかったことからも、「普通の」農家ではなかったことが想像される。
それでも、科学的な視点で試行錯誤を続けた長五郎は、明治元年に「清温育」を確立し、同3年に清温育を広めるための事業を始める。それが「高山社」であった。高山社では、近隣の農民に無償で養蚕技術を指導した。そこには長五郎の、国や地域の発展を願う高い志があったのだろう。
しかし高山社の無償の教育は、高山社指定の蚕種を農家が購入することによって成立していたという側面もある。現代でいえば携帯電話の契約で「端末代が実質無料!(ただし月額6,000円のパケット代2年縛り)」みたいな仕組みだったわけだ。その観点では、高山社は清涼育という看板を掲げた「実質無料ビジネス」を確立したという意味で称賛されるべき案件なのである。
「清涼育」は高山社を他の蚕種業者と差別化し、新たに養蚕に参入しようとする人々を囲い込むためのツールだったのだろう。注目すべきはそのビジネスモデルであって、「寒いときには加温、暑いときには換気」というような現場レベルのテクニックにだけ目を向けたのでは、なかなか高山社のすごさは理解できないように思う。
さて、いまから数ヶ月の後には「富岡製糸場と絹産業遺産群」の世界遺産登録の可否が判明する。この時点で予測を書くのは勇気がいることだが、実際に高山社を見学してみての私見では、富岡製糸場と他の遺産群との関係性が希薄であるという点、また、富岡製糸場以外の遺産の「有形文化財」としての弱さから、本当に4点セットで登録されるべきなのだろうか、と懐疑的になってしまった。
富岡製糸場の価値はかなり高いので、富岡製糸場単独での登録か、大急ぎで新町紡績所を国重文に指定して、ペアでの登録というのが理想的なように思えてならない。
(2013年08月18日訪問)