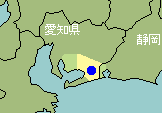龍源寺。音羽町の北部の山あいにある禅寺。
近くまで行けば本堂の屋根が見えるだろうと当て込んで、広い車通りを走っていたが、寺の場所がわからずに行き過ぎてしまった。
細い旧道を戻りながら丁寧に見ていくと、寺の谷の入り口に石門があった。期待できそうな寺である。

寺の周囲は棚田の続く浅い谷地で、見通しが利かない。
駐車場に車を置くと、まず薬医門がある。通称黒門と呼ばれているそうだ。江戸初期の門と見られている。(ということはおそらくこの寺で最も古い建物であろう。)

黒門を過ぎて左手に折れると、白壁が続いている。周りはちょっと密植ぎみの杉林になっている。

参道は右に折れて石段になっており、二重門と袴腰鐘楼が見えてくる。
田舎の禅寺としては最上の部類であろう。

二重門の左右には回廊がある。

だが、この回廊はまだ真新しくて、他の伽藍と密着していないところが玉にキズだ。
田舎の回廊付き禅院は私が最も好きな伽藍配置なので、普通はとても強く印象に残り、あとですぐにでも思い出せるものなのだが、この寺の回廊に限っては、こうして写真を整理する段になって「あ、そういえばここにも回廊があったんだっけ!」と再確認するありさまなのである。

袴腰鐘楼にしても、楼門の右側にあるというのはセオリー通りなのだが、普通は回廊は袴腰の部分にめり込んでいて、袴腰の内部でL字型に通路が曲がっているというのが一般的な造りである。この寺では回廊が袴腰の手前で終わってしまっている。
確かに、楼門や他の堂宇の配置からすれば、この寺にはもともと回廊があったと考えるのが自然なのだが、再建された回廊があまりにもおざなりで中途半端な感じがするのが惜しまれるのである。

納屋には大きな釜や桶などがあり、かつては修行僧がいたと思わせる名残があった。

本堂。

裏手には位牌堂。

本堂の左回りに90度の位置には禅堂。
この位置も田舎の禅宗の禅堂の位置としてはセオリー通りと言っていいだろう。
(2001年10月07日訪問)