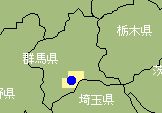群馬県で養蚕農家の町並みといえば、重伝建の赤岩とか、国指定史跡の島村などが検索で見つかると思うが、実感としてはその2箇所を見て、「養蚕集落ってこんな場所なんだ」と理解するのは少し現実とは違う気がしてならない。
以前に、富岡市の機足集落を紹介したが、今回紹介する東平井も、私の実感としてのオススメの養蚕集落だ。

養蚕という産業が、町並みや民家の外観に最も強く影響したのは明治後半から戦前までだろう。
戦後の養蚕は数字の上ではピークがあるが、ナイロンや後進国との価格競争で、コスト削減と大量生産に向かった。建物も納屋のような小屋での生産が中心となり、養蚕のために豪華な母屋を建てることがなくなってゆく。
この東平井の集落は、多くの建物がおそらく戦前であり、養蚕が民家の外観に影響を与えた最後の時期の養蚕集落の風景をよく留めていると思う。

明治~戦後すぐまでは、二階建ての母屋内で蚕を飼育することが多く、人が寝ている横で蚕を飼うとうことが普通だった。この写真の家の母屋などはそういう建物だ。
しかしそれでは日常生活に困るし、防疫学が進歩する中で消毒の重要性が増してくれば、寝起きする場所での養蚕はむずかしくなり、母屋の他に蚕室を建てるようになっていく。
奥に見える茶色い建物が蚕室だ。

昭和30~40年になると、国から補助金が出て農家はこのような巨大な蚕室を建て、さらに大規模に養蚕をするようになっていく。このクラスだとおそらく年間で数トンの繭を生産したことだろう。当時テレビでは「大きい~ことは、いいことだ~」などと歌うCMが流れ、養蚕も規模競争にしゃにむに突き進んだ。それはまるで戦前の大艦巨砲主義を彷彿とさせる。だが結果として10倍以上の価格差がある中国産繭との価格の戦いに勝つことはできなかった。この蚕室はさながら戦艦大和のようなものなのかもしれない。
(2008年12月30日訪問)