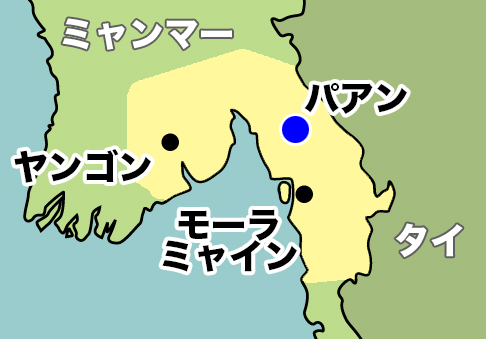AH1号線をタイ国境方向へたどる旅がつづく。最初の町らしい町であるエインドゥを過ぎると、左手に険しい山並みが見えてくる。

その山の山腹に小さなパゴダがあることは、以前に仕事のスタッフがターマニャヒルへ連れていってくれたときに気付いた。取り立てて観光寺院というわけでもないだろうから、そのときはただ場所を覚えておき、こうして自分で出直してきたのである。

山門はアーチが3つ重なった平板のデザイン。
その堂々とした姿から観光で入ってもOKっぽい印象を受ける。
もっとも、観光寺院でなくても入るわけだが・・・。

山門から寺までは500mくらい離れていた。
途中は畑が続く。

寺の入り口に到着。
屋根付きの石段があるので、ここで履物を脱いで行くことにする。

石段の脇では、僧が何か整地のような作業をしていた。
ハードワークである。上座部仏教の国では、お坊さんは基本的に労働をしないとされているが、カレン州ではお寺の補修などをする姿をよく見かける。
結局この寺で見かけた人は、このお坊さんだけだった。

石段は狭く、人がすれ違うのがやっとというくらい。

途中にあった僧房。

上のほうにある文字は、ミャンマー語ではない。なんとなく漢字と似ている。ミャインジーグー文字と言われるものではないかと思う。
僧房の寄進者のリストか。
2010年にこの僧房ができたのだろうか。それにしては建物が古びているが。

斜度もゆるいし、距離も短いので息切れするまえに丘の上に到着。

石段を上り切ったところにあった、船型の建物。
何かに使われる前に廃虚になりつつある。

階段の正面には講堂があるが、その通路は狭く、暗い。

天井付近には説話画が描かれている。ミャンマーでは珍しいものではないのだが、漆喰の表面に描かれたものが剥落して、実際以上の古さを醸し出している。

カタコンベなどに描かれた初期キリスト教絵画を見ているような感じだ。
もちろんこれらはせいぜい20年くらい前に描かれたものだろう。

アーチを多用した講堂の内部もどことなくキリスト教の教会を思わせる。
奥の鉄格子がついているところが、内陣である。

内陣の内部の様子。
中央の仏陀は王様の服を身に着けている。
全部で7体の仏陀があることから、過去七仏を表わしているのではないか。

講堂の横には仏教説話を再現したジオラマがある。仏陀が悟りを開いたあと、初めて説法をしたという「
釈迦がはじめに説法をしたのは、一緒に修行をした5人の仲間「
釈迦は当時の既存の宗教家に教えを受けたり、6年間のハードな修行も行った。その過程で、むやみに自分を苦しめるだけでは悟りは得られないと気付いた。

そしてブッダガヤという場所で、村の娘スジャータから乳粥の施しを受けて鋭気を養った。それを見た修行仲間は、釈迦が堕落したと思って釈迦の元を去ってしまった。
釈迦は悟りを得たあと、かつての5人の仲間の元を訪ねた。仲間たちははじめ釈迦の話を聞こうとしなかったが、ひとりまたひとりと悟りを得て、はじめて5人の仏が誕生した。

二人の神様の像。
もしかして釈迦に最初の説法をするように説得に来た梵天であろうか。いわゆる「梵天勧請」の場面。
奥まったところに鐘がある。狭い場所を細かく仕切って利用しているのがおもしろい。

建物から外へつづく狭い通路があった。

コンクリで作られた浅い水たまりがここにもあった。
タンバッタィンドゥエイパゴダにあったクレーター状の設備と同じものだと思われる。

水たまりの先は階段になっているので、仏塔の基壇へ上がるときに足洗い場なのかもしれない。

ふもとから見えた仏塔の基壇に上がってみた。

パゴダとセットで建てられるタコンタイ(石柱)には、小さな仏像がたくさんはめ込まれている。

パゴダの横にあった建物。
残念ながら中は見ることができなかったので用途は不明。

寺の背後の切り立った山までは意外に距離がある。
寺はその手前の独立した丘に建っており、背後の山とのつながりはなさそうだ。見回しても山頂パゴダなども見当たらなかった。
この寺院には立派な仏像や建物があるわけでもないし、鍾乳洞などのアイテムがあるわけでもない。だが廃虚じみていて、寂しくなるようなその雰囲気には、ミャンマーのオモシロ寺院とはちがった風情がある。
私にとってはここが今回のミャンマー滞在で一番気に入ったお寺であった。
(2014年07月13日訪問)