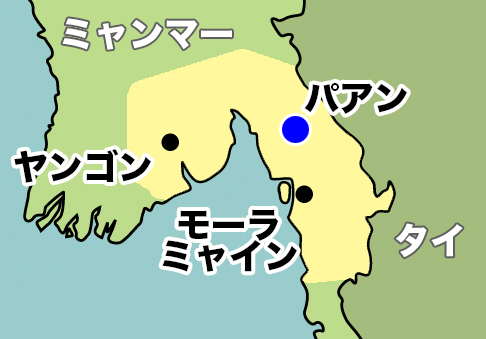次に向かったのは、右岸の寺。
この山はパアケッ山といい、パアン市の名前の由来となったカエルの伝説の中で、カエルがもともと棲んでいたとされる場所だ。「パア」は「カエル」、「ケッ」は「貼り付く」というような意味らしい。
その伝説については、シュエインミョウパゴダの記事で細かく書いたのでそちらを参照のこと。

サルウィン・パアン橋の西詰めから側道に入り、小さな村を抜けたところにお寺の入口があった。
門が閉じている。
もう夕方なので閉門してしまっているのだろうか。日が長い季節とはいえ、午後5時半である。

よく見ると、門の横に階段のついた通路があり、ここで靴を脱げとか書いてある。
どうやらこの階段から入っていいようだ。
野良犬が入らないようにしてあるのかもしれない。

階段を乗り越えて入り、中でサンダルを脱ぐことにした。
境内にはいると、長い回廊が伸びている。

途中にあった僧房。

森の中にあった仏殿。
日本の、というか、中国の仏殿のイメージに近い建物だ。森の中にあるため薄暗くて、ちょっと気味が悪い。

仏殿の中の様子。
まさに仏殿と言ってよい建物だ。
この寺の建物らしい建物は僧房と仏殿だけだった。

境内の奥のほうには仏塔エリアがある。
このエリアへの順路は、地面の上を歩かなければならないため、ちょっと足の裏が痛い。

仏塔エリアへ到着。
崖に寝釈迦や仏像、小さな仏塔がいくつも貼り付くように建っている。

崖の上のパゴダまで登る道がありそうだ。

ここには洞窟があるというのだが、カギが掛かっていて中には入れなかった。
もう夕方なので営業時間を過ぎてしまったのか。

扉の隙間から中を覗いてみたら、けっこう奥が深そう。
そして奥のほうに土嚢みたいなものが並んでいる。もしかしてグアノを詰めた肥料袋か。

岸辺にある仏像のところに登ると、サルウィン・パアン橋がよく見える。

パアケッ山へ登ってみよう。ただしサンダルは山門のところに置いてきてしまったので、どんな岩場があっても裸足で進まなければならない。
途中ハシゴがなければいいけれど・・・。
鉄筋や鉄パイプでできた

最初の長い階段を登ると、その先には岩場が待ちかまえていた。
でもすぐ流血するようなザクザクした岩でないのが救い。何とか登ることができた。外国人が裸足で進めるギリギリのルートだろう。

細い階段を登っていく。
高所恐怖症の人は、とりあえず後ろを振り向かないことだ。

最後の階段。
ハシゴがなくてよかった・・・。

山頂のパゴダへと到着。
ここは岬になっていて、サルウィン川方向180度の展望がある。

下流方向の眺め。
中央にサルウィン・パアン橋。
右奥に見える小さな2つの山は、今回の滞在中なんとか行ってみたいと思っている場所だ。

上流方向の眺め。
中央の中島の小山の上にもパゴダが見える。どうやったらあの島に行けるのだろう。
定期航路などはなさそうなので、市内の河港で小舟をチャーターすることになるのか。

帰ろうと思ったら、洞窟の前に地元の人たちが何人か集まっていた。
洞窟が閉じていたのは営業時間外だったからなのか、何時までに来たら洞窟に入らせてもらえるのか質問したが、どうも英語が通じない。
だが「これからコウモリが出てくるから、帰らずに時間になるまでここに居なさい」と言ってるみたいだ。
その言葉を信じて、約1時間、岸辺の仏像のところでぼーっと待っていた。
時刻は午後6時半、とつぜん崖の穴からキーキーという鳴き声が聞こえたかと思ったら、おびただしい数のコウモリが飛び出してきた。




現地の人たちが、ポリタンクをバンバン叩いている。
コウモリを追い立てているのだ。

1万、2万という数ではないと思う。
おそらく、10万から100万頭くらいのいるのではないか。群れの先頭はサルウィン・パアン橋よりもさらに先まで延びており、群れの全長は2kmにもなるだろう。

15分かかって大きな群れは途切れたが、それでもまだ出遅れたコウモリたちが穴から飛び出していた。
いったいこれほどの数のコウモリが洞窟の中でどうやってひそんでいたのか、まさに自然の驚異としか言いようがない。

いつまで見ていてもキリがないし、境内はもう真っ暗になってきたので、帰ることにした。
この日は、これまでになく遅い時間まで寺巡りをしていたのと、帰り際にお寺の人に営業時間を訊いたという2つの偶然が重なって、このイベントを知ることができた。もし別の日、昼間にこの寺を訪れていたら何も知らずに終わっていただろう。後日、職場のスタッフに訊いても誰もこの場所のことを知らなかったくらいなのだ。
ほんと、執念深く寺巡りをしていたら、一期一会ってあるものだな。
この洞窟は「バットケーブ」と呼ばれているようだ。私の手元にあるガイド本『lonely planet』にも掲載されていないが、パアン観光では最大の見物のひとつと言っていいのではないかと思う。
カレン州が外国人に開放されてまだ間もないが、これから外国人の観光客が増えたら、この寺はかなりの観光名所になっていくだろうと思う。
(2015年05月01日訪問)