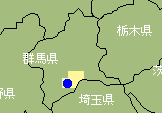西松田という字にあった稚蚕飼育所を探したが見つからず、近くに龍源寺という寺があったので立ち寄ってみた。
遠目には回廊のように見える建物がある。群馬県ではこれまでに回廊のある禅寺が確認されていないので、そうであれば大発見なのだが。

近くまで行ってみると、残念ながら回廊ではなく、薬医門になにか別の小屋が接続したもののようだ。
建物は新しく、築十年は経っていないであろう。

薬医門を裏側からみたところ。右側は阿伽井屋、左側は信徒休憩所になっていた。

この薬医門、言いようによっては三間一戸といえなくもなく、脇の二間分には仁王像が納まっている。
つまり、構造上は三間一戸薬医門であり、機能的には仁王門ということである。

信徒休憩所の内部。
休憩所の隣には東司がある。

境内に入ると、本堂は意外に小さく、庭木も邪魔して全景は撮影しにくかった。
寄棟の妻入りの建物であり、あまり本堂っぽくもない。寺の沿革が書かれた石碑によれば、他の場所にあったのが山崩れでこの地に引越してきたのが江戸初期、明治26年に焼失、本堂の再建は昭和51年だったという。比較的新しい時代なのはわかるが、宮大工の仕事ではないように見受けられる。
本堂の左側には小さな太鼓橋があり魚籃観音があった。

本堂の右側は庫裏になっている。

奥に行くと、無縁仏のピラミッドがあった。
舟形向拝の仏像型の墓や、駒型の墓が多い。江戸初期から前期の墓石だと思われる。この寺の引越の時期に建てられたものだろう。

その近くにあった別の墓石。このように「○○家の墓」のような墓は近代のものだ。昔は、個人や夫婦でひとつの墓石を建てていた。また、このような四角柱で上部が面取りしてあるような形は明治以降のものだと思う。
気になったのは碑銘にある「出牛家」。「でうし」とか「じゅうし」と読み、「デウス」が転訛したものという説があり、北関東では隠れキリシタンを先祖にもつ家系だとも言われる。

裏山のほうに、蚕影山大権現跡地という看板があったので行ってみた。
蚕影山とは養蚕の神様で、筑波山のすぐ南にある蚕影山神社を分祀したものであろう。
群馬県は養蚕が盛んな県と言われているが、どうも養蚕の神様は茨城県方面に多いようで、群馬県内には目立った養蚕の神様がない。話を聞くと、迦葉山にお参りしているケースが多い。

跡地は更地になっていて、石碑だけが建っていた。

寺の周囲は、明るい里山だった。
(2008年12月29日訪問)