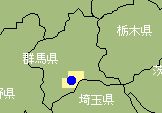「
鳥居は、

一の鳥居から社殿まで、200mほどの参道が続いている。
大きなケヤキが立ち並ぶ風景は、なんだか“武蔵野の古社"というおもむき。群馬県というよりは埼玉県などでありそうな風景だ。

参道は砂敷きで、流鏑馬が行われるという。
土師神社の祭神は、日本書紀に登場する野見宿禰という人物で角力(相撲)が強かったため相撲の神様とされている。また、天皇が崩御したときに殉死する者の代わりに埴輪を作ることを考案したともいう。
この神社のすぐ北には、埴輪窯跡という国指定史跡もあるので、なんらかの関連も感じさせる。(あ、埴輪窯跡、寄り忘れた・・・)

参道の途中には「辻相撲」の跡とされるものがある。辻相撲とは、道ばたや境内などで開催された民間の相撲。
案内板によれば、この土俵は「日本三辻相撲のひとつ」と書かれている。残りの2つは、大阪の住吉大社、石川県唐戸山とされているそうだ。おそらく、多くのブログが脊髄反射的にその説明を転記していると思われるが、この情報の典拠はあるのだろうか。残りの2つの物件に対して、かなり知名度が違う気がするのだが。

参道の突き当たりには、割拝殿というか長床というか、そんな感じの建物がある。
割拝殿ということにしておこうか。

この割拝殿の屋根はトタンがかぶせてあるが、合掌造りで、たぶん檜皮葺き。

割拝殿をくぐると左側に神楽殿。

正面は入母屋の本殿。
ガラス戸が三方にある明るい拝殿だ。年代は江戸中期だろうか。

相撲の額が奉納されている。

本殿は一間社流造でわりと大きめ。

海老虹梁の力強い感じや、雲模様のシンプルさは、拝殿よりは年代が古いのではないかと思わせる。

本殿の右側には神庫と神馬舎。

なんだか本格的な神馬舎だ。実際に中に生きた馬を入れることができそう。
流鏑馬のときに馬を待機させるのに使うのかもしれない。

社務所は無人のようだった。
(2008年12月30日訪問)